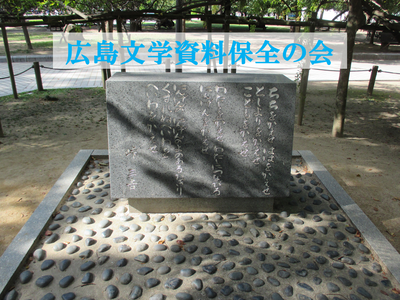大田 洋子
(1903~1963)

小説家。1903年広島県山県郡(現在の北広島町)に生まれる。大田洋子は“原爆作家”と呼ばれる以前からすでに女性作家として名を成していた。昭和元年(1926)に上京して菊池寛の指導を受け「女人芸術」同人として活躍。昭和14年(1939)には『桜の国』が朝日新聞懸賞小説に当選。東京から疎開、妹宅(広島市中区白島九軒町)に身を寄せていて原爆に遭遇。『屍の街』は、大田洋子の原爆被爆後の第1作。障子紙やちり紙まで使って懸命に書き続けた。1963年12月取材で宿泊中の旅館で急死。60歳没。
大田洋子 主な作品
- 小説
大田洋子 年譜
大田洋子 年譜
1903年
11月20日、広島県山県郡原村(旧豊平町。現在の北広島町)中原において、父・福田瀧次郎、母・トミの長女として生まれる。本名は初子。
1905年
弟・久が生まれる。
1908年
弟・一三が生まれる。
1910年
両親が離婚。山県郡都谷村(旧豊平町。現在の北広島町)の横山家(母・トミの実家)に移る。
4月、都谷村の尋常高等小学校に入学。
12月28日、山県郡津浪村(旧加計町。現在の安芸太田町)の大田家の養子となる。
1912年
母・トミが、広島県佐伯郡玖島村(旧佐伯町。現在の廿日市市)吉末の地主・稲井穂十と再婚。後にこの時の出来事として、日本映画界黎明期に名を残した玖島村出身の映画監督・枝正義郎の事が、『流離の岸』に書かれている。
初子(洋子)は、祖母・横山ツルと都谷村でしばらく暮らすが、やがて稲井家に引き取られる。先妻の子の鉄操・鉄鳴が新たに弟となる。
4月、玖島尋常高等小学校(のちの廿日市市立玖島小学校。2015年に閉校。)尋常科に転校。
1913年
妹・雪枝が生まれる。
1916年
3月28日、玖島尋常高等小学校尋常科を卒業し、4月、同校高等科へ入学。
この頃から、父・穂十の蔵書を読みふけるようになる。
妹・礼子が生まれる。
1918年
3月28日、玖島尋常高等小学校高等科を卒業。
4月13日、広島市の進徳実科高等女学校(現在の進徳女子高等学校)本科に入学。
1919年
妹・一枝が生まれる。
1920年
3月26日、進徳実科高等女学校本科を卒業し、4月同校研究科へ入学。
1921年
3月26日、進徳実科高等女学校研究科を卒業。
1922年
11月25日、広島県安芸郡江田島村(現在の江田島市)の切串補習学校の裁縫教師となる。
1923年
1月1日、「藝備日日新聞」に、短編小説『悩める人々』が掲載される。
3月8日から6月29日にかけて、同紙に教師達を登場人物とした恋愛小説『或る一群』が連載される。
9月30日、切串補習学校を退職。
『或る少年の気持』 新聞掲載。
1924年
タイピストとして、広島県庁に就職。
『二人の憂鬱』新聞掲載。
10月10日、元芸備日日新聞の安留愛子主宰の『廣島女流作家選集』(チウリップ社)に、『彼女たち』が掲載される。
1925年
大阪毎日新聞広島支局の記者・藤田一士と出会い、結婚する(しかし、のちに藤田に妻子ある事が判明する)。
1926年
藤田と別れ、上京。文藝春秋社の菊池寛の秘書となる。
半年で帰広し、再び藤田との生活を始める。
1928年
男児を出産するも、他家にもらわれる事になる。
大阪に移り、中央の雑誌に原稿を送り始める。
1929年
6月1日、近代女性作家の草分けである長谷川時雨主宰の『女人藝術』誌に、『聖母のゐる黄昏』で文壇デビュー。以降同誌を中心に作品を発表する。
この頃の作品にはプロレタリア風のものが多いが、結局は性格的・肉体的にその潮流に入っていけなかったと後年述べている。また、作品そのものの評価より、マスコミに真杉静枝・矢田津世子との(美人)三羽ガラスといった扱われ方をされ、ゴシップ記事に苦しむ。
1930年
5月頃に上京する。実家の稲井家が、玖島の家屋敷・地所を手放す。
1931年
9月1日、『火の鳥』誌に『火華開かず』 連載開始。
1933年
前年に『女人藝術』が廃刊となり、他の雑誌にも短編・随筆などを発表してはいたが、やがて低迷する事になる。同誌の精神を引き継いだ機関紙『輝ク』に、一時帰郷していた広島から原稿を送る。
父・穂十死去。
1936年
興中公司社員の黒瀬忠夫と結婚。
1937年
黒瀬と離婚。自伝的小説『流離の岸』の執筆を始める。
1938年
東京朝日新聞創立50周年記念1万円懸賞小説募集が発表。母・トミの勧めと援助もあり、小説の材料を求め、中国の天津・北京に渡航する。
年末に帰国し、『櫻の國』の執筆を始める。
1939年
『中央公論』誌2月号において、短編小説『海女』が、知識階級総動員懸賞第一席当選として発表される。
12月20日、初の著書『流離の岸』が小山書店より刊行される。
1940年
1月1日、朝日新聞紙上に、小倉緑の変名で応募していた『櫻の國』の第一席当選が発表、一躍注目を浴びる。
3月12日から7月12日にかけて同紙に連載。
5月1日、短編集『海女』が、中央公論社より刊行される。
5月、日本橋高島屋ホールにおける「輝ク部隊海軍記念日週間」初日に円地文子・長谷川春子らと公演を行う。
5月23日、中国中部に駐留の日本軍への慰問団「輝ク部隊」に加わり、神戸港を出発。
10月20日、長編小説『櫻の國』が、朝日新聞社より刊行される。
1941年
4月17日、大政翼賛会文化部の「輝ク会文化部」を発展させた、日本女流文学者会の設立が「輝ク」において発表される。円地文子・真杉静枝とともに、洋子は会長となった長谷川時雨を補佐していたものと思われる。
6月17日、復帰した城夏子の小説『神の鞭』において、長谷川時雨や洋子が歪められた内容で書かれた事について、女性作家の品位に関わると批判した書評 『小説とモデルの関係』が、『輝ク』に掲載される。
8月1日、短編集『淡粧』が、小山書店より刊行される。
9月15日、短編集『友情』が、報国社より刊行される。
11月1日、松竹映画『櫻の國』が封切られる(監督:渋谷実、主演:上原謙・高峰三枝子)。
1942年
1月1日、『新女苑』誌に『真昼』 連載開始(後の『真昼の情熱』。1年間連載)。
5月20日、短編集『星はみどりに』が、有光社より刊行される。
11月15日、短編集『野の子・花の子』が、有光社より刊行される。
1943年
3月18日、初の随筆集『暁は美しく』が、 赤塚書房より刊行される。
3月20日、短編集『たたかひの娘』が、報国社より刊行される。
10月1日、宇野千代編集・発行の『女性生活』誌に、戦前最後の長編小説と思われる『青潮』連載開始。
1945年
1月、空襲の続く東京を離れ、広島市白島九軒町の妹・中川一枝宅に疎開。
2月1日、『新青年』誌に、戦前最後の作品と思われる『白雁』が掲載される。
4月、内臓を患い、広島日赤病院に3ヶ月入院。佐伯郡玖島村への疎開の準備を始める。
8月6日、原子爆弾に遭遇、母・トミ、妹・一枝親子とともに、3日間を太田川神田橋付近の河原で野宿する。召集中の弟・鉄操は爆死する。
8月10日、佐伯郡玖島村楢原の広谷旅館に避難。後に同地の松本商店に落ち着くが、この山村でも放射線の影響による死者が増えていくのを見て死を覚悟し、古障子紙等ありあわせの紙を使い、『屍の街』を執筆し始める。
8月30日、降伏調印の直前、朝日新聞に送った『海底のような光~原子爆弾の空襲に遭って』が掲載される。
冬頃、同地の玉藤家に移る(1978年発見の未発表原稿『冬』『冬の巣』の舞台となる)。
1946年
『屍の街』を中央公論社に送るが、アメリカ進駐軍の検閲体制のため発表を断念される。
4月、戦後初の作品と思われる『青春の頁』が、広島の婦人雑誌『新椿』誌に連載される。
11月、原爆や広島といった言葉を伏せ、初めて活字化された原爆作品『河原』が『小説』創刊号に掲載されるが、別の作家の作品が検閲に引っかかり、出版禁止となる(1948年2月号に再収録、2003年にアメリカで再発見)。
1947年
1月、佐伯郡和村(旧佐伯町。現在の廿日市市)河津原の江島家において、『屍の街』を執筆した事で、 呉に進駐していたアメリカ軍の尋問を受ける。
1月15日、長編小説『真昼の情熱』が、戦後初の著書として丹頂書房より刊行される。
5月頃、安芸郡江田島村の共産党員・筧中静雄と結婚(後、離婚)。
9月頃、東京に戻る。
1948年
3月1日、長編小説『情炎』が、新人社より刊行される。
11月10日、プレスコードが緩み、一部削除された『屍の街』が、中央公論社より刊行される。
1949年
1月1日、中原淳一主宰の人気少女雑誌『ひまわり』に、『ホテル・白孔雀』連載開始(1年間連載)。
3月6日、新日本文学会東京支部会員となる。
12月15日、少女小説集『春の訪ずれ』が、東光出版社より刊行される。
12月25日、長編少女小説『ホテル・白孔雀』が、ポプラ社より刊行される。
1950年
1月、『ひまわり』誌に、少女小説『黄なるくちなし』連載開始(1年間連載)。
5月30日、完全版『屍の街』が、冬芽書房より刊行される。
この年から、睡眠薬と鎮静剤を常用するようになる。
1951年
8月15日、長編小説『人間襤樓』が、河出書房より刊行される(その年の第4回女流文学賞を受賞)
暮れに、原爆作品に取り組んだ影響か不安神経症と診断され、東大病院神経科に入院。睡眠持続療法を受ける。
1952年
7月1日、原爆作品を書き続ける事に対する批評家の揶揄について、その所感を書いた『作家の態度』が、『近代文学』誌に掲載される。以降、原爆文学論争が活発化する。
1953年
7月22日、新日本文学会平和委員会委員に選出される。
1954年
5月5日、短編集『半人間』が、大日本雄弁会講談社より刊行される。
(『半人間』は芥川賞候補となり、12月には1954年度平和文化賞を受賞)
1955年
10月25日、長編作品『夕凪の街と人と』が、講談社ミリオンブックスとして刊行される。
1956年
1月31日、前年に病気をしていた大原富枝への友情から、壺井栄・池田みち子・中本たか子・畔柳二美・芝木好子・森三千代・佐多稲子とともに作品を持ち寄り、『静か雨~現代女流作家名作選~』を現代社から刊行。原爆作品以外のジャンルで、新たな傾向を示した短編『紫真珠』(初出は1953年)掲載。
3月1日、ビキニ環礁での水爆実験による第五福竜丸事件にあわてふためく日本の姿を皮肉って、「ざまをみろ」と書いた短編『半放浪』が、『新潮』誌に掲載される。また、放浪のような旅が多くなっていく。
4月1日、NHK第一放送で、ラジオドラマ『流離の岸』が放送される。
6月21日、近代映画協会・日活による映画『流離の岸』が公開される(監督:新藤兼人、主演:北原三枝)。
1957年
8月5日、第3回原水爆禁止世界大会第4分科会 「被害対策及び被害者救援について」に出席する。
1959年
この年、母・トミが死去。年末に家の登記済権利書を預け、壺井栄らに金を借りる。後に返済をめぐって喧嘩するが、だんだんと作品の依頼が減っていく。
1961年
8月10日、生前最後の著書となる短編集『八十歳』が、講談社より刊行される。収録作の『八十歳』『八十四歳』は女流文学賞候補となり、新境地を開いたとされた。
1963年
6月、胆管結石(十二指腸と肝臓障害の疑い)で東京女子医大病院内科に入院。8月、東京聖路加病院内科に転院。9月、神経科専門病院晴和病院に転院。11月退院。
10月25日、久々の長編小説『なぜその女は流転するか』が、週刊新聞「新婦人しんぶん」において連載開始。
12月10日、『なぜその女は流転するか』の実在モデルの取材のために訪れていた福島県耶麻郡猪苗代町大字蚕養字沼尻山の旅館五葉荘で入浴中、心臓麻痺で急死。享年60歳。
(絶筆となった『なぜその女は流転するか』は、翌年2月27号の第63話をもって連載終了。未完。)