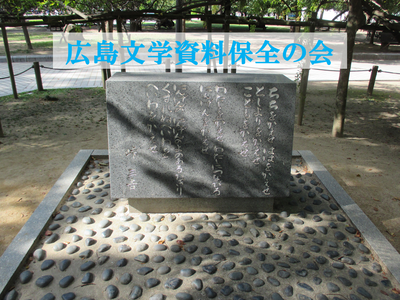原民喜『心願の国』
原民喜が死の直前に書き綴った短編小説。死後の同年5月、『群像』ではっぴょうされた。
被曝の前年に亡くなった妻への哀悼や家族への愛情を叙情的に回想しつつ、同時に死への憧れも綴られた、原の代表的な作品の1つ。
自身の周りにある風景の描写を通して、静かに別の世界へ行くことこそが、自分にとって最も自然なことだと告げており、その表現から、現代日本文学史上もっとも美しい散文といわれている。
〈一九五一年 武蔵野市〉
夜あけ近く、僕は寝床のなかで小鳥の啼声をきいてゐる。あれは今、この部屋の屋根の上で、僕にむかつて啼いてゐるのだ。含み声の優しい鋭い抑揚は美しい予感にふるへてゐるのだ。小鳥たちは時間のなかでも最も微妙な時間を感じとり、それを無邪気に合図しあつてゐるのだらうか。僕は寝床のなかで、くすりと笑ふ。今にも僕はあの小鳥たちの言葉がわかりさうなのだ。さうだ、もう少しで、もう少しで僕にはあれがわかるかもしれない。……僕がこんど小鳥に生れかはつて、小鳥たちの国へ訪ねて行つたとしたら、僕は小鳥たちから、どんな風に迎へられるのだらうか。その時も、僕は幼稚園にはじめて連れて行かれた内気な子供のやうに、隅つこで指を噛んでゐるのだらうか。それとも、世に拗ねた詩人の憂鬱な眼ざしで、あたりをじつと見まはさうとするのだらうか。だが、駄目なんだ。そんなことをしようたつて、僕はもう小鳥に生れかはつてゐる。ふと僕は湖水のほとりの森の径で、今は小鳥になつてゐる僕の親しかつた者たちと大勢出あふ。
「おや、あなたも……」
「あ、君もゐたのだね」
寝床のなかで、何かに魅せられたやうに、僕はこの世ならぬものを考え耽けつてゐる。僕に親しかつたものは、僕から亡び去ることはあるまい。死が僕を攫つて行く瞬間まで、僕は小鳥のやうに素直に生きてゐたいのだが……。
今でも、僕の存在はこなごなに粉砕され、はてしらぬところへ押流されてゐるのだらうか。僕がこの下宿へ移つてからもう一年になるのだが、人間の孤絶感も僕にとつては殆ど底をついてしまつたのではないか。僕にはもうこの世で、とりすがれる一つかみの藁屑もない。だから、僕には僕の上にさりげなく覆ひかぶさる夜空の星々や、僕とはなれて地上に立つてゐる樹木の姿が、だんだん僕の位置と接近して、やがて僕と入替つてしまひさうなのだ。どんなに僕が今、零落した男であらうと、どんなに僕の核心が冷えきつてゐようと、あの星々や樹木たちは、もつと、はてしらぬものを湛へて、毅然としてゐるではないか。……僕は自分の星を見つけてしまつた。ある夜、吉祥寺駅から下宿までの暗い路上で、ふと頭上の星空を振仰いだとたん、無数の星のなかから、たつた一つだけ僕の眼に沁み、僕にむかつて頷いてゐてくれる星があつたのだ。それはどういふ意味なのだらうか。だが、僕には意味を考へる前に大きな感動が僕の眼を熱くしてしまつたのだ。
孤絶は空気のなかに溶け込んでしまつてゐるやうだ。眼のなかに塵が入つて睫毛に涙がたまつてゐたお前……。指にたつた、ささくれを針のさきで、ほぐしてくれた母……。些細な、あまりにも些細な出来事が、誰もゐない時期になつて、ぽつかりと僕のなかに浮上つてくる。……僕はある朝、歯の夢をみてゐた。夢のなかで、死んだお前が現れて来た。
「どこが痛いの」
と、お前は指さきで無造作に僕の歯をくるりと撫でた。その指の感触で目がさめ、僕の歯の痛みはとれてゐたのだ。
うとうとと睡りかかつた僕の頭が、一瞬電撃を受けてヂーンと爆発する。がくんと全身が痙攣した後、後は何ごともない静けさなのだ。僕は眼をみひらいて自分の感覚をしらべてみる。どこにも異状はなささうなのだ。それだのに、さつき、さきほどはどうして、僕の意志を無視して僕を爆発させたのだらうか。あれはどこから来る。あれはどこから来るのだ? だが、僕にはよくわからない。……僕のこの世でなしとげなかつた無数のものが、僕のなかに鬱積して爆発するのだらうか。それとも、あの原爆の朝の一瞬の記憶が、今になつて僕に飛びかかつてくるのだらうか。僕にはよくわからない。僕は広島の惨劇のなかでは、精神に何の異状もなかつたとおもふ。だが、あの時の衝撃が、僕や僕と同じ被害者たちを、いつかは発狂ささうと、つねにどこかから覘つてゐるのであらうか。
ふと僕はねむれない寝床で、地球を想像する。夜の冷たさはぞくぞくと僕の寝床に侵入してくる。僕の身躰、僕の存在、僕の核心、どうして僕は今こんなに冷えきつているのか。僕は僕を生存させてゐる地球に呼びかけてみる。すると地球の姿がぼんやりと僕のなかに浮かぶ。哀れな地球、冷えきつた大地よ。だが、それは僕のまだ知らない何億万年後の地球らしい。僕の眼の前には再び仄暗い一塊りの別の地球が浮んでくる。その円球の内側の中核には真赤な火の塊りがとろとろと渦巻いてゐる。あの鎔鉱炉のなかには何が存在するのだらうか。まだ発見されない物質、まだ発想されたことのない神秘、そんなものが混つてゐるのかもしれない。そして、それらが一斉に地表に噴きだすとき、この世は一たいどうなるのだらうか。人々はみな地下の宝庫を夢みてゐるのだらう、破滅か、救済か、何とも知れない未来にむかつて……。
だが、人々の一人一人の心の底に静かな泉が鳴りひびいて、人間の存在の一つ一つが何ものによつても粉砕されない時が、そんな調和がいつかは地上に訪れてくるのを、僕は随分昔から夢みてゐたやうな気がする。
ここは僕のよく通る踏切なのだが、僕はよくここで遮断機が下りて、しばらく待たされるのだ。電車は西荻窪の方から現れたり、吉祥寺駅の方からやつて来る。電車が近づいて来るにしたがつて、ここの軌道は上下にはつきりと揺れ動いてゐるのだ。しかし、電車はガーツと全速力でここを通り越す。僕はあの速度に何か胸のすくやうな気持がするのだ。全速力でこの人生を横切つてゆける人を僕は羨んでゐるのかもしれない。だが、僕の眼には、もつと悄然とこの線路に眼をとめてゐる人たちの姿が浮んでくる。人の世の生活に破れて、あがいてももがいても、もうどうにもならない場に突落されてゐる人の影が、いつもこの線路のほとりを彷徨つてゐるやうにおもへるのだ。だが、さういふことを思ひ耽けりながら、この踏切で立ちどまつてゐる僕は、……僕の影もいつとはなしにこの線路のまはりを彷徨つてゐるのではないか。
僕は日没前の街道をゆつくり歩いてゐたことがある。ふと青空がふしぎに澄み亘つて、一ところ貝殻のやうな青い光を放つてゐる部分があつた。僕の眼がわざと、そこを撰んでつかみとつたのだらうか。しかし、僕の眼は、その青い光がすつきりと立ならぶ落葉樹の上にふりそそいでゐるのを知つた。木々はすらりとした姿勢で、今しづかに何ごとかが行はれてゐるらしかつた。僕の眼が一本のすつきりした木の梢にとまつたとき、大きな褐色の枯葉が枝を離れた。枝を離れた朽葉は幹に添つてまつすぐ滑り墜ちて行つた。そして根元の地面の朽葉の上に重なりあつた。それは殆ど何ものにも喩へやうのない微妙な速度だつた。梢から地面までの距離のなかで、あの一枚の枯葉は恐らくこの地上のすべてを見さだめてゐたにちがひない。……いつごろから僕は、地上の眺めの見をさめを考へてゐるのだらう。ある日も僕は一年前僕が住んでゐた神田の方へ出掛けて行く。すると見憶えのある書店街の雑沓が僕の前に展がる。僕はそのなかをくぐり抜けて、何か自分の影を探してゐるのではないか。とあるコンクリートの塀に枯木と枯木の影が淡く溶けあつてゐるのが、僕の眼に映る。あんな淡い、ひつそりとした、おどろきばかりが、僕の眼をおどろかしてゐるのだらうか。
部屋にじつとしてゐると凍てついてしまひさうなので、外に出かけて行つた。昨日降つた雪がまだそのまま残つてゐて、あたりはすつかり見違へるやうなのだ。雪の上を歩いてゐるうちに、僕はだんだん心に弾みがついて、身裡が温まつてくる。冷んやりとした空気が快く肺に沁みる。(さうだ、あの広島の廃墟の上にはじめて雪が降つた日も、僕はこんな風な空気を胸一杯すつて心がわくわくしてゐたものだ。)僕は雪の讃歌をまだ書いてゐないのに気づいた。スイスの高原の雪のなかを心呆けて、どこまでもどこまでも行けたら、どんなにいいだらう。凍死の美しい幻想が僕をしめつける。僕は喫茶店に入つて、煙草を吸ひながら、ぼんやりしてゐる。バツハの音楽が隅から流れ、ガラス戸棚のなかにデコレイシヨンケーキが瞬いてゐる。僕がこの世にゐなくなつても、僕のやうな気質の青年がやはり、こんな風にこんな時刻に、ぼんやりと、この世の片隅に坐つてゐることだらう。僕は喫茶店を出て、また雪の路を歩いて行く。あまり人通りのない路だ。向から跛の青年がとぼとぼと歩いてくる。僕はどうして彼がわざわざこんな雪の日に出歩いてゐるのか、それがぢかにわかるやうだ。(しつかりやつてください)すれちがひざま僕は心のなかで相手にむかつて呼びかけてゐる。
我々の心を痛め、我々の咽喉を締めつける一切の悲惨を見せつけられてゐるにもかかはらず、我々は、自らを高めようとする抑圧することのできない本能を持つてゐる。(パスカル)
まだ僕が六つばかりの子供だつた、夏の午後のことだ。家の土蔵の石段のところで、僕はひとり遊んでゐた。石段の左手には、濃く繁つた桜の樹にギラギラと陽の光がもつれてゐた。陽の光は石段のすぐ側にある山吹の葉にも洩れてゐた。が、僕の屈んでゐる石段の上には、爽やかな空気が流れてゐるのだつた。何か僕はうつとりとした気分で、花崗石の上の砂をいぢくつてゐた。ふと僕の掌の近くに一匹の蟻が忙しさうに這つて来た。僕は何気なく、それを指で圧へつけた。と、蟻はもう動かなくなつてゐた。暫くすると、また一匹、蟻がやつて来た。僕はまたそれを指で捻り潰してゐた。蟻はつぎつぎに僕のところへやつて来るし、僕はつぎつぎにそれを潰した。だんだん僕の頭の芯は火照り、無我夢中の時間が過ぎて行つた。僕は自分が何をしてゐるのか、その時はまるで分らなかつた。が、日が暮れて、あたりが薄暗くなつてから、急に僕は不思議な幻覚のなかに突落されてゐた。僕は家のうちにゐた。が、僕は自分がどこにゐるのか、わからなくなつた。ぐるぐると真赤な炎の河が流れ去つた。すると、僕のまだ見たこともない奇怪な生きものたちが、薄闇のなかで僕の方を眺め、ひそひそと静かに怨じてゐた。(あの朧気な地獄絵は、僕がその後、もう一度はつきりと肉眼で見せつけられた広島の地獄の前触れだつたのだらうか。)
僕は一人の薄弱で敏感すぎる比類のない子供を書いてみたかつた。一ふきの風でへし折られてしまふ細い神経のなかには、かへつて、みごとな宇宙が潜んでゐさうにおもへる。
心のなかで、ほんとうに微笑めることが、一つぐらゐはあるのだらうか。やはり、あの少女に対する、ささやかな抒情詩だけが僕を慰めてくれるのかもしれない。U……とはじめて知りあつた一昨年の真夏、僕はこの世ならぬ心のわななきをおぼえたのだ。それはもう僕にとつて、地上の別離が近づいてゐること、急に晩年が頭上にすべり落ちてくる予感だつた。いつも僕は全く清らかな気持で、その美しい少女を懐しむことができた。いつも僕はその少女と別れぎはに、雨の中の美しい虹を感じた。それから心のなかで指を組み、ひそかに彼女の幸福を祈つたものだ。
また、暖かいものや、冷たいものの交錯がしきりに感じられて、近づいて来る「春」のきざしが僕を茫然とさせてしまふ。この弾みのある、軽い、やさしい、たくみな、天使たちの誘惑には手もなく僕は負けてしまひさうなのだ。花々が一せいに咲き、鳥が歌ひだす、眩しい祭典の予感は、一すぢの陽の光のなかにも溢れてゐる。すると、なにかそはそはして、じつとしてゐられないものが、心のなかでゆらぎだす。滅んだふるさとの街の花祭が僕の眼に見えてくる。死んだ母や姉たちの晴着姿がふと僕のなかに浮ぶ。それが今ではまるで娘たちか何かのやうに可憐な姿におもへてくるのだ。詩や絵や音楽で讃へられてゐる「春」の姿が僕に囁きかけ、僕をくらくらさす。だが、僕はやはり冷んやりしてゐて、少し悲しいのだ。
あの頃、お前は寝床で訪れてくる「春」の予感にうちふるへてゐたのにちがひない。死の近づいて来たお前には、すべてが透視され、天の気はすぐ身近かにあつたのではないか。あの頃、お前が病床で夢みてゐたものは何なのだらうか。
僕は今しきりに夢みる、真昼の麦畑から飛びたつて、青く焦げる大空に舞ひのぼる雲雀の姿を……。(あれは死んだお前だらうか、それとも僕のイメージだらうか)雲雀は高く高く一直線に全速力で無限に高く高く進んでゆく。そして今はもう昇つてゆくのでも墜ちてゆくのでもない。ただ生命の燃焼がパツと光を放ち、既に生物の限界を脱して、雲雀は一つの流星となつてゐるのだ。(あれは僕ではない。だが、僕の心願の姿にちがひない。一つの生涯がみごとに燃焼し、すべての刹那が美しく充実してゐたなら……。)