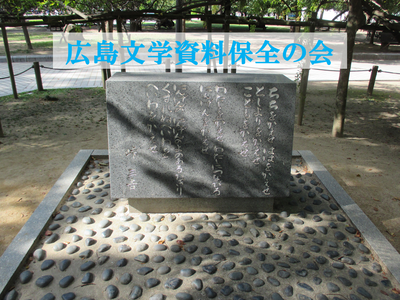原民喜『行列』
あんまり色彩のない家々と道路が文彦の眼の前にあつた。それでも、太い電信棒の頭には飴色の光線が紛れ込んでゐて、二月の青空は奇妙に明るかつた。人物の影や形が少し青みを帯びた空気のなかに凍てたまま動いてゐた。金粉を塗つた竜の首や、青銅色の蓮の葉や、葬式に使ふ、いろいろの道具が賑やかに路上を占めてゐた。そこに立留つて見物してゐる人間は、溷(こん)濁した表情で、静かに時間が来るのを待つてゐるのだつた。近所のおかみさんの顔や、通りがかりの年寄の顔がそのなかにあつた。顔が控目に文彦の家を覗いてゐた。
文彦は路上から自分の家の二階を見上げた。軒の天井に燕の空巣が白く見え、乾大根を吊した縄が緩んでずりさがつてゐた。昨夜、あそこの窓には白々と燈があり、烈風が電線を唸らせて通つて行つた。夏の宵にはあの軒に蝙蝠が衝き当るのだつた。文彦には知りすぎるほど知つてゐる場所の一つだつた。ふと、文彦の眼は玄関の格子戸に貼られた、忌中といふ文字に留まつた。たしか、叔父の筆蹟らしく、勢のいい文字が薄墨で滲み、悲しみを添へてゐた。その時、開放たれた戸口から、紋附を着た叔父の顔が覗き、何気なしに往来を眺めた。文彦はあわてて帽子を脱ぎ、おじぎをしたが、叔父の眼鏡の反射は白くたつぷり光つて、何の反応もなかつた。やがて叔父はそのまま奥の方へ引込んでしまつた。
文彦は玄関を潜り、鞄を放り出して、編上靴の紐を解き始めた。今放つた拍子に鞄のなかの弁当箱の箸が揺れて、ゴロゴロと音たてるのを聞きながら、彼はのそりと奥の方へ這入つて行つた。次の間の薄暗い女中部屋に、白木綿で覆はれた桶が、壁の方へ片寄せて置かれてゐた。覆ひをめくつてみると、木の香も新しい棺桶であつた。文彦は指でピアノを弾つやうに蓋の上を弾いてみた。
次の間からは、障子や襖が取除かれて、屏風が張られてゐるので、薄暗い家も広々とした感じであつた。線香の煙と、読経の声と、ひそひそ話と、畳の上を滑るやうにして歩く白足袋の音と、低い天井の下には沈んだ空気が立罩めてゐた。文彦は正面の柱時計を眺めた。三時二十分で、恰度彼が中学から帰つてくる時刻だつた。柱時計の下に立てられてゐる屏風は、虎の絵だつた。死んだ父が、幼い日の文彦に虎といふものを教へて呉れた屏風で、父が死んだ時も、たしか柱時計の下に立てられてゐたのを文彦は憶ひ出す。文彦が久振に見る屏風にみとれていると、すぐ眼の前に、大阪の叔母がやつて来た。四五年振りに見る、器量のいい、叔母の姿に、文彦はちらと頬を染めたが、叔母は風のやうに急いで台所の方へ行くのだつた。
文彦は縁側に出て、冷たい空気にあたりながら、服の釦をはづして、あくびをした。見るともなしに庭を眺めると、日あたりの悪い軒の梅はまだ固い蕾のままだつた。冬休みに彼が物置から引張り出して、弄んだ、古い扇風機のエレキが、今も庭の隅に放つたままになつてゐた。文彦は軽い空腹を覚え、母を探すために座敷の方へ行つた。
八畳の間には床がのべられ、恰度、人々は枕辺を取囲んで、ざわめいてゐた。文彦は静かに人々の後から死人の様子を覗いてみた。文彦の母の指が、顔の上に被さつた白い布をめくると、その下に文彦の死顔があつた。白蝋のやうな文彦の顔が現れると、人々はまた新しく泣き出した。唇のあたりに産毛が生え、顔に小皺がみえ、閉ぢてゐる目蓋が悲しさうな表情だつた。何処となしに、それは文彦の父の死顔と似てゐた。そのうちに、母は筆にコツプの水を含めて、死者の唇を湿した。文彦は唇が変に冷やりとした。筆は文彦の兄の手に渡された。兄の手はいくらか震へ、筆は鼻の下の方を撫でた。その次に妹が筆を執つた。幼い妹は習字でもするつもりで、文彦の唇を重たく抑へた。それから叔父の番であつた。叔父は軽く文彦の唇を撫でた。筆は大阪の叔母に渡された。見れば、叔母の睫毛にも露が光つてゐた。文彦も自然に涙が浮んだ。その時、叔母は軽く筆をやつて、すぐに次の人に渡した。
文彦は枕辺を離れて、仏壇の前に行つてみた。昼ながら賑やかに燈が点けられて、いろんな御供えものが上げられてゐた。その燦然と輝く金色の小さな欄干を眺めてゐると、文彦は二階が気になつた。階段を昇り、二階の勉強部屋へ入つてみた。何時の間にか、文彦の机や書物は隅の方へ取片づけられ、そこで女達が着物を着替へたらしく、茣蓙の上にしどけない衣裳の抜殻があつた。それでも壁の方には、黒リボンをつけた、文彦の写真が貼られてあつた。この正月撮つた写真だが、何かに脅かされて、ビクついてゐるやうな顔を見ると、文彦は自分ながら厭な気持がした。往来に面した方の窓から下を除いてみると、やはり、路には葬式屋が屯してゐた。さつきより、大分人数が増えたのは、いよいよ参列の人も揃つたのかもしれなかつた。
モーニングを着て、山高帽を被つた男が、ひよいと文彦の窓の方を見上げた。受持の山田先生だつた。先生のまはりには廿人ばかりもクラスの生徒がゐた。文彦はちよつと意外な気持がした。クラスでは除け者にされ、何時も冷笑されてゐたので呑込めないことであつた。それにしても、山田先生の何時もの愁はしげな顔はかういふ場所に応はしかつた。小学校で同級だつた、二三の女学生が映つた。これも意外なことであつた。そのなかの一人は、嘗て文彦が草履を盗まれて困つてゐた際に、何気なしに革の草履を彼の足許へ差出して呉れた生徒だつた。その草履の緒には赤いきれが目じるしに着けてあつた。文彦はその女学生の襟首に眼を注いだ。白い固さうな襟をきちんと揃へて、大変真面目さうな顔つきだつた。文彦はまた意外な人物を発見した。鳥打を被つて、襟巻をしてゐるその青年は、彼が学校を怠けて、郊外をぶらぶら歩いてゐる時など、きつと後からやつて来て、「先生につげ口してやるぞ」と脅すので、文彦は一度も相手にしなかつたのだつた。
文彦は顔を引込めると、今度は別の窓から違つた方向を眺めた。その窓の方には、ところどころ禿げた山脈が遠くに見え、少し近くに黒くこんもりした小さな山があつた。その小さな山で、文彦は今日一日、学校へ行かず、怠けて暮らしたのだつた。山は文彦をよく知り抜いてゐるやうな表情であつた。文彦は暫くその山を視凝めて、さつきまでの生活を考へてみた。今日、山の枯草の上で弁当を食べたり、遠くに見える海を眺めて、日向ぼつこをしてゐたのは、みんなたしかなことだつた。しかし、どうも階下の様子が気になつて、また薄暗い階段をドシンドシンと降りて行くと、座敷には何時の間にか、棺桶が運ばれてゐた。
今、掛布団がめくられて、白い帷子を着た文彦の死骸を、叔父と母とで抱へ起さうとしてゐるところだつた。余程、死骸は重たくなつてゐるものとみえて、どうかすると、二人の手を滑り抜けようとした。がくりがくりと死骸が反抗する度に、文彦は何か苛立たしく、同時に愉快でもあつた。白い道化た衣裳を着せられて、硬直してゐる姿は、哀れつぽいと云ふよりも滑稽だつた。ところが死骸が愈々抱へ上げられて、棺桶へ入らうとする時、幼い妹は恐怖のため、わーつと泣き出した。すると、また新たな悲しみをそそられたらしく、母や叔母はひきしぼるやうな泣き声を放つた。文彦は叔母がそんなにまで泣くとは思ひ掛けなかつたことで、やはり彼も一同の悲嘆につり込まれて、しくしく涙を啜り出した。しかし、死骸は母の手を離されたため、額が棺桶の縁に前屈みに伏さつてゐるので、文彦は額のあたりが疼くのを感じ、叔父の帯の間から洩れて来る、懐中時計のチクチクといふ響を聴いた。間もなく、叔父が文彦の額の位置を直し出した。叔父は文彦の両手を揃へて、膝の上で合掌させると、数珠を嵌めてしまつた。それで死骸が今は窮屈な姿勢に固定し、何か大へん恨みを持つてゐるやうな容顔だつた。
死骸は今にも飛起きて、暴れ出しさうだつた。その時、棺桶の片隅へ、叔父は黒い風呂敷包を挿入れた。文彦は何が包んであるのか気になつたが、そのためにか、死骸に閃いた不穏な気配は、暫く収まつて行つた。すると、叔父は桶に蓋をしてしまつた。その時、軒の廂に何の鳥か綺麗な小鳥がやつて来て、チヤチヤチヤと啼き出したので、一同の視線はふと期せずしてその方へ奪はれた。
「文彦はもう鳥になつてしまひました」と母は真顔で呟き、皆も静かに息を潜めた。けれども、無心な小鳥はそのまま何処かへ行つてしまつたので、また作業は続けられて行つた。叔父は金槌でコンコンと桶に釘を打ち込んだ。文彦はもう棺桶の内部を視ることが出来なかつたが、幽閉された闇に屈む死骸は、金槌の音で脊柱が揺らぎ、烈しく身悶えしてゐるらしかつた。ところが、人々の顔には、ほんの微かではあるが、何か晴々した表情が閃き始めた。母はハンケチを持出して、さつきからの涙を拭ひ、熱くなつた眼球を冷たい空気にあてながら爽やかな気分になつて行くらしかつた。叔母はもう間もなく往来へ出ることを予想して、ハンドバックを開けて顔をつくろひ始めた。皆は、ともかく一段落ついたやうな顔で席をはづし出したが、叔父ばかりは態と落着き払つて、釘の頭を丁寧に打込まなければ気が済まないらしかつた。最初に現れた、人々の冷淡さに、文彦は何か残念で耐らない気持をそそられた。そして、叔父が態と余計な事に念を入れてゐるのを見ると、一層癪に触るのだつた。
「叔父さん」と文彦は後から声を掛けた。「僕はまだこんなにピンピンしてるんだよ」と文彦は、釘を打つてゐる方の叔父の腕をおづおづと把へた。だが、その声はどうしても叔父の耳には入らない様子だつた。文彦は叔父が強情張つてゐるのだと思つた。
「やめてくれ、やめてくれ、僕の葬式の真似なんか、まつ平だ」と今度は力一杯で抗議し出した。すると、叔父は始めて文彦に気がついたらしく、凝と彼を睥み下したかと思ふと、はしと、金槌で文彦の頭を撲りつけた。文彦は眼から火の出るやうな痛みと、怒りで、今は幼い子供のやうに、わーつと泣き出してしまつた。そして、隣室の方の母のところへ駈けつけて行つた。
「叔父さんが撲つた、僕の額を撲つた。お母さんが悪いのだ、死にもしないのに葬式なんか出すからこんなことになるのだ」と文彦は精一杯、号泣しながら、畳の上で身悶えをつづけた。けれども母は文彦に気づかないらしく、そそくさと喪服の襟を正してゐた。文彦はまた凝としてゐられなくなつた。
「やめてくれ、やめてくれ、僕は死んぢやいないぢやないか。ほら、ここにゐるのがわからないのか。馬鹿、みんな馬鹿、みんなとぼけて僕を葬らうとするのか」と、今度は家のうちの誰彼なしに把へては喚いた。が、誰も彼の存在に気づかないらしかつたので、次第に文彦は気抜けがして来た。とうとう文彦は幼い妹にむかつて、
「おい、云うてくれ、僕がわかるだろう。そら、この通り僕はここにゐる」と、空の弁当箱を妹の耳許で振り廻してみた。すると、妹の顔には、ほんの微か、何かを凝視する表情が現れたが、それも無駄であつた。妹は向ふの壁にある鏡で彼女の顔を見てゐるにすぎなかつた。
文彦はもう一度棺桶をたしかめてみようと思つて、座敷へ引返した。すると、もう棺桶は玄関の方へ運ばれてゐて、恰度、人夫が柩に入れて担いで出るところだつた。人々は今、玄関からてんでに下駄を穿いて、外へ出て行つた。さつき脱いだ、編上靴がまだ其処にあつたので、文彦もあわてて靴の紐を結んだ。
外ではもう一同が整列してゐて、先頭の列は今静々と歩き出した。それはまるで始めから定められた秩序を着実に行つてゐるやうな落着を持つてゐた。もう先頭は文彦の家から半町あまり離れたところにゐた。道の両側や、家々の戸口から人が立並んで静かに見物してゐた。先頭は恰度四つ角の交番のあたりを通つてゐたが、交番の巡査も暫く葬式の列にみとれてゐるのだつた。誰もこの葬式に疑ひをさしはさむものはなささうだつた。今、西の空から投げかける夕方の光線を、龍の首は正面に受け、それは西の方へむかつて進んで行くのだつた。蓮の花を持つた男や、三方を抱へた男が、黙々と続いた。みんな、西の方を指して進み始めた。西の街はづれには火葬場があつた。
文彦は列の外側から、ずんずん先頭の方へ進んで行つたが、ふと、花輪があるのに気づいた。「北村文彦の霊前に」と、どういふ積りなのか、彼の名前が態々白布に誌るされて、花輪に吊されてある。文彦はそれを見ると、また気がくしゃくしやして、花輪を支げてゐる男の側に近寄つて行つた。
「そんな花輪やめてくれ」と、花輪を奪ひ獲らうと、手を伸した。すると、相手は穏やかに手を振つて、文彦の手を払ひ退けてしまつた。ほんとに文彦に気づいて、花輪を守つたかどうか疑はしい動作であつたが、その男の肘の力は、なかなかものものしいことがわかつたので、文彦は暫く途方に暮れた。見ると、すぐ側に、俥に乗つた坊さんがゐた。それは文彦の家にもよく出入りする坊さんなので、文彦も知らない人ではなかつたが、今、美しい法衣を着て悠然と俥上にゐるのを見ると、文彦はまた癪に触つた。
「やめてくれ、やめてくれ。こんな無茶な葬式出ささないぞ」と、文彦は車の轅を把へて呶鳴り出した。が、坊さんはただ面白さうに、にやにや笑つて、とりあはうともしないのであつた。それで文彦の方でも次第に気勢がだれて来た。
文彦は暫く路上に立止まつてぼんやりしてゐるうちに、行列はずんずん進んで、もう母も兄も妹も、彼の側を通り過ぎてしまつた。恰度、彼が気づいた時には、叔父が側を通りかかるところだつた。さつきも金槌で顔を撲られたので、文彦は多少躊躇したが、やはり思ひ切つて、叔父の側にとり縋つた。
「ねえ、叔父さん、僕はもう喧嘩腰でものは云はないから、まあ聞いて下さい。僕はそら、この通りピンピン生きてるのに、どうして皆は僕を死んだことにして、葬式なんか出すのか、その訳が教へてもらへないでせうか」
叔父は依然として不機嫌さうな顔で、
「死んだものは死んだ。だから葬式出すのだ」と云つたきり相手にしてくれなかつた。文彦はまた口惜しかったが、すぐに気を取り直して、行過ぎた母を追つて訴えた。
「お母さん、僕を、この生きてる方の僕をよく見て下さい。僕がわからないとはお母さんもよつぽどだうかしてゐるのです。ね、わかるでせう」すると母は不思議さうに、文彦を視凝めてゐたが、ふと、
「おや、文彦だね、迷ってるのだね」と、おろおろ声で云ふと、早くもハンケチを眼の縁に当てた。
「お母さんこそ迷つてるのだ。ひどいよ、ひどいよ、あんまり人を無視したやり方だ」と文彦は母の側で地蹈鞴を踏んで喚きながら、母の袂を把へて行かすまいと試みた。ところが母は、ますます文彦の存在を無視するばかりで、「可哀相に、まだ迷つてるのかい。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と、泣きながら念仏を唱へるので、手の下しやうがなかつた。文彦は今度は兄をとらへて談判してみた。
「兄さん、兄さん、僕が誰だかわかるだらう。わかるなら返事をしてみてくれないか」兄は黙つて頷いた。
「そら、わかるなら、何故葬式なんか出すのか、一つ君の考へを聞かせてもらひたいね」
すると、兄は、「そんなこと知らないよ」と云つて、そつぽを向いてしまつた。
「知らないつて、現に生きてゐる僕の身の上になつてみてくれよ。何と云つてもこれは変ぢやないか」と文彦はまた尋ねた。
「いや、そんなこともあるかも知れないね。一体この世の中で変でないものはない」と、兄は冗談とも本気ともつかない顔つきで、文彦を視凝め、「まあ、短気を起こすなよ」と云ふのであつた。文彦は困惑して、暫く立留つてゐる隙に葬式の列はずんずん前へ進んで行つた。それで彼もまた、ちよこちよこと忙しげに列の脇を追つて行つたが、今は誰を相手に話しかけようとしてゐるのやら見当がつかなかつた。
ふと、行列は電車通りを横切るので、一度留まつた。気がつくと、文彦の横に、山田先生がゐるのであつた。文彦は何か先生の方で云ひ出しはすまいかと、暫くもぢもぢしてゐた。しかし先生は相変らず、もの静かな顔で何も見てゐないやうな態度であつた。文彦はさつき迄、暴れ廻つたのがふと気恥ずかしくなつた。平素はおとなしい、火の消えたやうな無口の文彦が到頭飛込むところまで飛込んだのだつた。彼は山田先生の方へ一歩、歩み依ると、思ひきつて口をきいた。
「先生、僕です。何故こんな無茶をみんなはするのでせう」すると、山田先生は文彦を多少憐むやうな顔つきで、
「それは君にわかつてゐるだらう」と云つた。恰度その時電車が通り過ぎたので、列はぞろぞろと進み出した。先生のまはりにゐたクラスの生徒達は今までぺちやくちや喋つてゐたが、ふと一人が文彦の姿を認めると、
「やあ、あそこに北村がゐらあ」と騒ぎ出した。
「やあ、やあ、やあ、北村の幽霊か」と、皆は遽かに活気づいて、嬉しさうに囃し出した。
「生きてた時から、まるで幽霊のやうな野郎だつたもの。ハハハ、こいつは面白い」と、悪童の一人は、くるりと文彦の方へ向きかはると、挙手の敬礼をした。皆は一勢に口を開けて笑ひ出した。
「幽霊閣下に敬礼」と、またさつきの生徒は敬礼をした。文彦は恨めしさうに皆の悪口を見守つてゐたが、ふと我慢がならなくなつて、「黙れ」と叫んだ。すると、二三秒、皆は吃驚したやうに沈黙したが、忽ち一人の皮肉屋が云つた。
「やあ、幽霊が口をきいたぞ。古今未曾有だな」さうして、皆は再び騒然とした。文彦は今にも泣き出しさうな顔で口惜しさを堪へた。「静粛にし給へ」と、その時、山田先生が皆を叱つた。皆はそれでも、じろじろと、列から顔を離しては、文彦の方へ軽蔑の視線を投げた。とうとう文彦は路上に立留つて、暫く皆の通過するまで待つた。さうしてゐるうちに、列は次第にしんがりの方になつて来て、文彦の小学時代の友達などの顔がちらほら見えた。が、彼等は文彦に遠慮してか、顔を外けて通り過ぎた。そして、とうとう最後になつた。一番しんがりには、文彦の家に永く働いてゐる老女が、普段着のまま列から大分後れ勝ちに歩いてゐた。そこには、とりのこされた安らけさがあつた。
老女は文彦を認めると、別に驚きもせず、口をきいた。
「なかなか賑やかな葬式で御座います」文彦は老女と並んで歩き出した。「しかし、これは誰の葬式なのかしら」と、彼はもう興奮しないで話すことが出来た。
「それは、あなたのお葬式なので御座いますよ」文彦はこの老女とこれまで殆んど口をきいたことがなかつたが、今は不思議に彼女の云ふことがしんみりと聞けた。
「それで僕はどうなるのかしら」
老女は暫く黙つてゐたが、「あなたは葬られるので御座いますよ」と答へた。
「葬られると、僕は滅びるのかしら」
「ええ、勿論で御座います」
「でも、僕はまだピンピン生きてるではないか」
「いいえ、あなたはあの柩のなかに収められてゐます」
「ぢやあ、ここにゐるのは誰なのかしら」
「それはあなたの抜け殻で御座いますよ」
文彦は暫く黙つて歩いてゐたが、黙つてゐるのが次第に怕くなつた。
「不思議だね、僕はずつと昔、子供の時、自分が死んで、葬式を出される夢をみたことがあるんだが、その時も自分で自分の葬式に従いて歩いたり、皆が泣けば僕も泣いたのだつた」
老女はちらつと若やいだ顔をして文彦を視凝めた。
「ああ、そんな夢なら、私もずつと以前にみたことが御座います」
「しかし、あれは夢でよかつた、が、今度は、今度は……」と、文彦はガタガタ戦きながら啜り泣いた。
「いいえ、今度だつて、まあまあ夢のやうなものですよ、観念なさいませ」と、老女は静かに文彦を宥めた。暫くして文彦は泣き歇むとまた口をきいた。
「僕は何度も普段から、死にたい、一そのこと一思ひに死んでしまひたいと思つてはゐた。しかし、かう云ふ変な目に遇はうとはまるで考へてゐなかつた」
「ええ、あなたは段々諦めが出来てまゐりました。さあ、もう二つ目の橋にまゐりましたから、焼場も間もなくです」と老女は静かに向ふを指差した。恰度、橋の中程を文彦は歩いてゐた。向岸の家々からは夕方の支度をするらしい煙が幾条も立昇つてゐた。その少し川上の方の、枯木のなかに、大きな赤煉瓦の煙突が高く聳えてゐた。今も、薄い微かな煙が昇つてゐて、その上の空を鴉が四五羽、頻りに舞つてゐた。
「ほんとに、これは夢であつてくれないかなあ」と文彦は絶望して呟いた。
「ええ、さうした嘆きなら、誰だつて何時も抱いてをりますとも」老女もそつと溜息をついた。
「ぢやあ、やつぱり僕はほんとに焼かれてしまふのかね」老女は黙つて頷いた。
「さうか、僕は子供の時、地獄の鬼が赤い車を牽いて迎へに来る夢をみたことがるが、やつぱし焼かれた後ではあんな赤い車が迎へに来るのかね」老女は何も返事しなかつた。列はもう橋を渡つて、堤にさしかかつた。
「そら、あなたは大分前、夏に伯母さんの葬式に行つたことがあるでせう。あの時この辺に葦簾が張つて御座いました」と老女は云つた。その辺には二三軒飲食店が並んでゐた。
「さうだつた。この辺に置座が出てゐて、ラムネやサイダがバケツに浸けてあつた。この辺は夕涼みの場所なのだらうね」
「あの時のお葬式は途中で大変な雷が鳴りました」
「あ、さうだつたね。みんなびしよ濡れになつて帰つたもの」
「今日のお葬式は恰度いい天気で幸で御座います」気がつくと、むかふの方の空が美しい夕焼であつた。それはもう春のやうに明るい雲の加減であつた。文彦はふと、また溜息をついて呟いた。
「ああ、もう一度、川の堤で土筆を摘んでみたい」
すると、老女は頑に頭を振つて云つた。「もうそんなことはおつしやいますな」
焼場の石の門が見えて来た。行列の先頭の方はもう静々と其処を潜つてゐた。文彦と老女は暫く黙つたまま歩いてゐたが、そのうち二人とも石の門へ来た。空地に今、会葬者が参列してゐた。正面の寂れた丈の高い建物は、かなり急な勾配の屋根で地面に迫つてゐた。その屋根の下に、白い壁や、太い柱や、祭壇らしいものが見えた。蝋燭の灯が燃えてゐた。文彦の柩はその前にあつた。柩の両脇に、花輪や、龍の首や、造花などが、とりどりに置かれた。左右の椅子には母や兄や親戚の者が腰を下してゐた。一般の会葬者は一塊になつて空地に立つてゐた。文彦と老女は一番端の方から、遠くの祭壇を眺めた。椅子にかけてゐる母は今頻りにハンケチを出して眼を拭ひ出した。ふと文彦は兄の席に目をやつた。あの隣の椅子に文彦は嘗て腰掛けたことのあるのを憶ひ出した。
次第に人々の影は暮色に包まれて濁つて行つた。坊さんは今、だみ声で読経をあげてゐた。今は何も彼も色の褪せた写真のやうな気持がして、父が死んだ時のうつろな悲しみと似てゐた。文彦はふと別のことを思ひ出して老女に話しかけた。
「あ、僕はうつかりしてた。今日学校を怠けて山で遊んでゐたのだが、懐中時計を樹の枝に置いたままで忘れて帰つた。あとで拾つておいてくれないか」老女は黙々と頷いた。
広島花幻忌の会『雲雀』第4号、2004年、58~67ページより
(初出は「三田文学」昭和11年9月号)