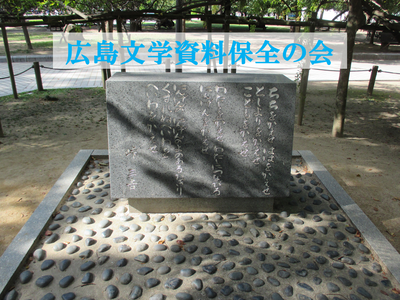原民喜『幻燈』
堤の埃つぽい路を川に添つて昂は溯ってゐた。月の光が波の行手を白く浮上らせてゐたが、ざわざわと揺れる藪や、思ひがけない処にある家屋の灯が昂のおぼつかない気持を通過した。時々足に纏わる、相撲草や、飛立つ昆虫などもあつたが、それらは昼間の熱気をまだ少し貯へてゐた。粘土質の柔かい埃には埃の匂ひがあつて、それが彼に遠い日の記憶を甦らせた。昂は七つ八つの頃、夏の夕方露次に立つて好きな女のこのことを躊躇ひがちに懐つた。その女の眼が神秘な湖水であつた。しかし、今彼は二日ばかり前にみた夢のことが不意と気掛になつた。それは何処か大きな河を渡つていくと、橋の袂に料理屋があつたのだが、そこに料理屋があつたことが夢のなかで非常に詠嘆的に感じられたのだつた。で、後になつて考へ出すと、彼は一度でもいいから、あけみをさうした場所へ連れて行き度いのだつた。夢のなかで感じたのもたしか、あけみを連れて料理屋なんかへ行けたためなのだが、しかし、今も何処かそんな願望の世界へむかつて彷徨つてゐた。では、一体何処にあの料理屋があるのだらう、―あけみは今も狭い家で睡つてゐて、台所では彼の母がごくごくと音をたてて食器を洗つてゐるに違ひないのだが、昂は遥かに遠方を眺めて歩いた。そこには月光で暈された繁みが水に映つてゐた。あのあたりまで行くと、更に眺めが展けて来る筈なのだが昂はどこまで今溯つて行くのか見当がつかなかつた。夢のなかの料理屋、―あれは確か一ヶ月位前誰かから聞かされた話のやうな気もする。そして、その話とあの夢と何の連絡もないのにまだ気にかかつてゐた。昂は自分のその何時もの癖を強ひて押除けようとはしなかつた。言葉も動作も思考までもが吃るのだが、それに腹を立てればきりがなかつた。
すぐ近くに淵があるらしく、ひたひたと川波の音が聴えて来た。子供の頃、狽は一日うつとりとして、ここの川を溯つたことがあつた。彼を連れて歩いた男の記憶はもうはつきりしなかつたが、牛が鳴いてゐて、蓮華草の花が咲いていたから、季節は四月らしかつた。をかしいことに昂はその大人が何かの秘密のために彼を連れて歩くやうに妄想した。赤ん坊のお前は川から流れて来たのだよ、と昂の父はよく笑ひながら云つた。もしそれがほんとなら、彼の生れた家は川上にあるらしかつた。さうした心配と多少の夢につつまれてゐた過去が、今もそのあたりの叢に揺曳してゐた。昂はひたひたと呟く水の音で、月の光がゆらゆらと映つてゐる姿を思ひつめてゐると、稍微かな睡気を誘ふのであつた。実際、空に懸つてゐる月ははつきりしない感銘であつた。月光のためにすべてのものが吐息をついてゐた。そして昂が視凝めて歩いてゐる世界は、もう今日の昼間の続きではなく、もつと安らかなものになり変つてゆくやうに想へた。恰度その時、四五間さきの傍の薮から何か黒い塊が現れた。昂は藻抜けの殻になつたやうな足どりで進んで行くと、その黒い塊は彼を目掛けて突進して来たが、彼の足もとまで来ると、きりりと一回転しておきながら、不意と緩やかに伸び上つて、彼の左手に突当たつた。瞬間、どきりとしたが、既にそれは子犬であることがわかり、遠方へよろよろと走り去つてゆくのを見送ると、昂は再び何事もなかつたやうに静かな散歩をつづけた。ひやりとした犬の触感は消え、掌の咬傷は浅く痛みも微かであつたので、昂にはたつた今眼の前に生じた事件もすぐにも光に暈されて遠ざかつて行くのであつた。さうした、ぼんやりした気分ではあつても、絶えず昂に附纏ふのは、あけみのことであつた。ねむれ、ねむれ、ねむれと昂は胸のうちで呟いた。さうすると、微かな睡気が、歩いてゐる彼の顔にも、月の光と一緒に降りそそいで来るのであつた。あけみは今も家で睡つてゐるに相違なかつた。もつと遥かなあけみが別の世界にゐて、その透明な玻璃窓に射し入る月の光を頬に浴びながら睡つてゐる有様が昂には描かれた。その別の世界にゐるあけみなら、何時までも妨げられることなく睡れるだらうが、昂の妻は時々眼を醒すのであつた。しかもこの頃では二時間と続けて意識が保てず、箸を持つたまま、或は箒を持つたまま、睡魔に襲はれては、うとうとするのだつた。
あけみの不思議な病気の傍で昂はもう一年あまりも暮らして来たが、あけみは何時覚めるとも知れない睡りのなかを漾つてゆくやうなものだつた。それでも結婚の頃には余程の努力が払はれてゐたのだらう、あけみは普通の健康らしかつた。それが日とともにまた娘時代の状態に逆戻りして、そして睡眠を催す度が却つて頻繁になつた。それと同じやうに昂は暫くの間殆ど全治してゐた、吃音の癖がこの頃ではまた烈しくなつて来た。生活の労苦や、昂の過去に受けた沢山の屈辱の記憶などが、頻りと彼の神経を掻立て、さんざんに彼を愚弄した。しかし、昂にとつては、あけみは重荷ではあつても、どうかすると彼の方からそれに縋らうとするのであつた。あけみの体温を傍にして、寝呼吸に聴入つてゐれば、何時の間にか昂の心も純白となり、焦燥の心も静めら、やがてうとうととした仮睡のなかにぼんやりとした巨母の姿が微光を放つ。今もその微光は昂の頭上に降り注いだ。昂は何時の間にか大分上流まで来てゐた。河原の白砂の上にも月の光が煙つてゐた。夏の終りの月は何か苦悩をそそるやうに空に懸つてゐた。昂はやうやく立留まつて、熊笹の脇の空地にしやがんだ。ここから家まで引返すのは大変であつた。何のためにぼんやりと散歩をつづけてゐたのか、昂自身にもはつきりしなかつた。何かを求めて彷徨つて行つたやうでもあるし、何かに追駆けられて逃げて来たやうでもあつたのだ。しかし、昂は眼をあげて、そこの河原の中央に細く流れてゆく水を視ると、ふと、病的な気分に襲はれた。今、自分の生涯がここでばつたりと行塞がつて、もう前へも後へも引返されないやうなもどかしさが、それを、もどかしさと感じささない静的なものとなつて蹲つてゐた。大体、この頃昂は、悲嘆に似た気持で、己の過去を溯つてゆく癖が出来てゐたが、それにしても今夜ほど憮然とした姿で散歩したのは稀であつた。急に昂は立止まつて家へ引返さうと思つた、すると、一瞬身体全体がめりめりと音をたてて陶器のやうに砕ける幻想が泛んだ。
そして、昂はその夜家へ引返し、それから何日かは普通の状態で暮したのであつた、あの月夜のふらふらした気分とは似ず、昂は昼間の業務に追はれながら、あけみと母と暮した。ある夕方、ふと悪寒がするので昂は畳に伏して、天井板を眺めた。すると、天井板の節穴がふと眼についたはずみに、それが忽ち絶体絶命の凶兆かのやうに彼の視線へ対つて弾丸の如く飛びかかつて来た。昂は眼を閉ぢて、襲ひ掛つて来る悪寒を払はうとした。その時、精神も肉体もぐつたりと異様な疲労を呈して、沼の底にでも引込まれて行くやうに滅入るものがあつた。きんきんと金属製の音響が耳許で生じ、その一振動毎に彼の毛穴に戦慄が点火されて行つた。暫くすると昂の寝てゐる畳はぐるぐると急速に廻転し始めた。それから終には高く低く波を打つて来て、昂の肉体は何かの魔力によつて絞り上げられた。昂は肩を縮めて、のた打ち廻つた。そのうちに苦悩が少し緩められて来た。濁つた壁のやうなものが墜落すると、彼の前にはぼんやりとした景色が現れた。月の夜の河原を昂は歩いてゐた。月光は埃のやうに彼の前に煙つてゐて、竹薮がざわざわと揺れた。竹薮の上の方の空に鍵に似た黒い影が浮んでゐたが、昂はそれを訝る気持で、なるべく視まいと努めて、地面を視て歩いた。ところがふと、何気なしに眼をその黒い点にやると、今迄動かなかつた黒い影は遽かに地面へ対つて滑り落ちて来た。それから非常に緩い速力で、しかし確実に昂に対つて近寄つて来るのだつた。昂の足もとに来た時、それは犬であつた。が、昂の周囲を一回転するのが何分間もかかつた。昂はやがてその犬に腰の骨を噛みつかれるのを感じて、悶えながら立留つてゐた。犬は昂の肩に前足を掛けると、その重みが昂には頭の芯まで伝はつて行つた。昂の背後にゐる犬はこの時もう牛位の大きさになつてゐた。そして犬は更に河馬ぐらいの大きさに変つて行つた。やがて、ぱくりと口を開くと、昂の身体は大きな歯の間に噛締められた。痛みは鈍く、鋭く昂の全身に伝はつていく。昂の神経は熱湯を注がれたやうにちりちりとした。そのなかを更に針のやうに光るものが暴れ狂つて走つた。それだのに全身はもう犬の歯にしつかりと締めつけられてゐて、抜け出すことが出来ない。時々痙攣が生じて、無力な逃走を試みる。昂は犬の歯の間から逆しまに頭を垂れて、ふと下界を眺めた。真白な河原の砂に月の光が幽霊のやうに燃えてゐる。と、その砂のなかを犬の眼に似た水が音もなく流れてゐた。水がぼうつと、一ケ処燐光を放つた。次いであつちからも、こつちからも焔が生じて、もう川は真赤な水の流れであつた。それがずんずん昂を目がけて流れて来る。
やがてこの真赤に煮え滾るところの液体が昂を襲つた。彼の鼻腔や耳にまで熱気は侵入し、煙が全身から立昇つた。今焔の洪水のために、昂はもう犬の歯から押流されてゐた。轟々と唸る火の渦に巻込まれながら、猶ほさまざまの火の姿が昂に戯れて来た。硫黄や砒素などの恨しさうな火の玉が来ると、昂の内臓は破壊に脅え、顔は断末魔の形相を湛へるのであつた。すると、猶ほちょん切られてピリピリ動く蜥蜴の尾のやうに、昂の頭に纔か(わずか)に残されてゐる知覚に、自分の断末魔の物凄い姿が映つて、その恨しさうな顔に怖れて昂は叫ぶ。叫んだ筈なのが四つん這ひになつて吠えてゐるのだ。吠えて吠えて昂の咽喉は一本の細い針金のやうになつてしまふと、既に身体中の水分が蒸発してしまふ。この時、昂のぎよろんとした虚空の眼球にコップの水が映つた。誰の掌によつて支へられてゐるのか、その透明なコップのむかうには白い水仙の花に似た塊があつた。昂はすさまじい勢でコツプに這ひ寄つて、唇もて、その懐しい水に触れようとした。けれども、次の瞬間には昂の咽喉仏は痙攣を始め、水であつたコツプからは煙が立ち昇るのであつた。痙攣は嘗ての日、彼の発音器官を無惨に辱かしめたやうに、今も彼の意志を逆に捩ぢ伏せてしまつた。昂の苦悩はここで一つの絶頂に達したが、やがて、なにものかが拳を挙げて昂を乱打すると、昂を組み伏せて、すつかり身悶え出来なくさせてしまつた。そして暗闇がその上を通過した。暗闇は汽車のやうに昂の顔の上を走つた。
走り去つた汽車が物悲しいサイレンを残すと、次第にあたりは夜明けの微光が漾つて来て、どうやら雨になるらしい気流が交はつてゐた。何時の間にか昂は暗い函のなかに小さく押込められてゐた。その函の上を荒縄で縛り、二人の男が棍棒で擔つて行くのだつた。今彼等は何を擔つてゐるのか一向無頓着な様子で、怒つた顔をして、黙々と歩いてゐた。硬い地面を踏んで行くものらしく、ゴトゴトと跫音がつづいた。函は揺れる度に軋り、それにつれて昂の骨はがくりがくりと外れさうになつた。到頭雨になつたらしく、雑草の叢が仄かに囁き出した。暫くすると、小川の近くに来たとみえて、水音が微かに聞えた。やがてその小川の岸を渡る時、前の方の男が川にむかつて唾液を吐いた。余程彼等は不幸な人間らしく、頭に雨がかかると忽ち水蒸気となつて昇つた。遠くの小屋で火を焚くのが、ゆらゆらと夢心地に昂には感じられた。時たま、何かの鳥が高く上を飛んでゐて、鋭く抉るやうな叫びを放つた。何処までこの二人の男は昂を擔つて行く気なのか、密閉された函の内部にゐてはわからなかつたが、彼等の歩行は何時まで経つても同じやうな調子だつた。一寸も急つてはゐないし、無理に遅らせてもゐないし、それだけに重苦しく耐へきれないものがあつた。不図、昂は耳許に年寄らしい男の、優しいだみ声が聞えて来た、それは何か悲痛を諦めてしまつてゐる人間の温かい呟きで、昂には次第にもの悲しく感じられた。しかし、声はそれきり杜切れてしまつて、後はまた二人の男の跫音ばかりであつた。その跫音はまるで木のやうに硬い。大粒の涙が浮んで、昂の目の縁で崩れると、ぽとりと落ちた。そして今函の外は朝である筈なのに、逆に夕暮が近づいて来る気配だつた。昏々と雨が降り募り、路は何時まで行つても涯てしなく、景色も次第に疲れて無惨になつてゆくらしい。昂の頭も_々とした闇が立ち罩め、その底に金色のぼんやりした暈が一つ微かに浮んで来て、それが静かに彼をあやしてゐるやうだつた。彼を運んでゐた男達のゴトゴトといふ跫音が何時の間にかしなくなつた。そして昂を閉込めてゐた函ももう消えてなかつた。気がつくと昂はある街角の路上に横たはつてゐた。真昼の雨降りの路上には一つも人影がなかつた。すぐ前の菓子屋の店頭はがらんとしてゐた。何処の店にも人はゐないのだつた。雨に清められた、路上の小石が美しく露出してゐた。軒毎に瓦斯の門燈があつたが、あれは夕暮脚榻をかかへた男が燕の如く現れて、一つづつ灯をさしてゆくのだ。何処かから馬車の喇叭が響いてきさうなのに、今はしーんとしてゐる。
そこは二十年も以前の、ある街角に違ひなたつたが、別に昂は訝りもせず、目隠しをされた馬や、蹄の音や、先走りの男などが現れて来るのを待つてゐた。ふと彼の側に何処からか女中がやつて来た。彼女は昂を認めると大変心配さうな顔をして、「まあそんなところに一人でゐらしたのですか、さつきから随分探してゐました、さあ、おうちへ帰りませう、お父さんがお待ちかねですよ」と云つた。そして昂の手を引いて、ずんずん歩いて行つたが、昂はその女中の温かい掌にぶらさがつて歩いた。やがて家に這入ると、薄暗くじめじめして其処は大きな洞穴のやうだつた。中央に机が置かれて、その上にランプがぼんやり点けられてゐた。女中は昂を机の脇まで連れて行くと、「只今戻りました」と挨拶した。すると、机には誰か淋しさうな影の薄い男が何か頻りに書きものをしていたが、ふいと顔をあげて、昂を睨んだ。「うまく釣られて来たな」とその男は破鐘のやうな大声で笑つた。見るとその男はもうさつきの男ではなかつた。おそろしく野蛮な骨相をした男で、顔中が威圧の筋肉で出来上つてゐる癖に、何か愉快さうに、にやにや笑つてゐた。「己を覚えてるだらうな」とその男は昂を斜に視下しながら嘯いた。昂は恐怖のあまり口がきけなく、ふと、さつきの女中の方に縋らうとして振りかへると、女中の顔は口が耳まで裂けた怪物になつてゐる。すると男は何か気に触つたらしく、忽ち机に一撃をあたへて怒鳴つた。「逃げようつてのか!」と男は眼を尖らして昂を射屈めた。机のランプがひつくりかやつて燃え出すと、彼はそれを掌で_んで床の上に投げつけた。その物音を聞きつけて、隣室から男が二人やつて来た。彼等は拳で昂を脅しながら、机の男にむかつて、慇懃に腰を屈めた。「この男を一つみてやつてくれ給へ」と机の男は何時の間にか穏やかな口調になつてゐた。二人の男はかしこまつて、また腰を屈め、それから昂の方へ向直つて、じろじろ眺めてゐたが、急に一人の男が気色ばんで昂の腕を_むと「来い!」と云つてずんずん歩き出した。コンクリートの廊下のやうな道を、二人の男は昂を真中に挟んでずんずん進んだ。非常に歩調が急いでゐて、そのまた反響がものものしかつた。その時昂の腕を_んでゐない方の男が、昂の耳許にずつと顔を近寄らせて、「愉快だな」と親密さうな調子で話しかけた。昂が黙つてゐると、その男はまた「愉快だな」と云ふので、昂もつい釣込まれて、「愉快だな」と云つた。すると、その男は遽かに冷やかな態度になつて、「何? 何だと、何が貴様に愉快なのだ」と怒鳴り散らした。「でででも……」と昂は詫びようとしたが口が吃つてしまつた。その男は昂の口許を忌々しげに眺めてゐたが、「だだまれ!」と叫んだ。が、その男は吃つて叫んだのを非常に残念さうにして、自分の方で黙つてしまつた。昂は何だかそれが気の毒になつて、相手の方を見ないで歩いた。
そのうちに吃つた方の男は何時の間にか、ふつと消えてしまつて、廊下のやうな道が尽きると稍々広い運動場に出てゐた。昂の腕を握つてゐた男は不意とその手を離して、昂の後方に廻つた。そして、びつくりするやうな大声で、「一、ニ、一、二」と号令を掛け出した。昂は一生懸命、歩調をとつて歩き出したが、後から叱咤するやうに「左、右、左、右」と号令を掛けられた。歩調が間違つてゐるのに気がついて、足踏みをするのだが、うまくゆかない。何度やつても歩調が乱れる。号令は昂をさんざ、まごつかせて置いて、後からどかんと怒鳴るつもりなのだらう、泰然として続けられる。気がつくと、昂を取囲んで中学時代の友達がにやにや見物してゐた。その見物のなかには女も二三人混つてゐる。昂は両脇からたらたら冷汗をかきながら、奥歯を食ひ締つて、目の前が茫々と白む想ひで、歩調をとつた。すると、突然、「まはれ右前へ」といふ怒号が耳許でして、「おい!」と号令は下つたが、昂は足を踏み損なつて失敗つた。再び、号令は「まはれ右前」と掛けられた。そして昂はまた失敗つた。また、「まはれ右前」と、号令が勇ましく掛けられた。昂は今度もまた失敗するのを予想すると、もう足が慄へて思ひ通り動かなかつた。彼が失敗る度に、見物の中学生達は面白さうに笑つた。歯を剥出したり、舌を出したりして、皆は彼の失敗を応援した。なかにも一人の女は脇の女にむかつて、さも昂を憐むやうな大袈裟な顔つきで何か囁いてゐた。昂は何が何だかもう号令が聞えなくなつて、立留まつた。すると、今迄遠くから号令を掛けてゐた男がつかつかと昂の脇に近寄つて来た。その男は何時の間にか教師の服装になつてゐたが、ポケツトからメートル差を出すと、昂の前に屈んで、昂の膝の関節から踵までの長さを計り出した。見物人は珍しさうに、ずつと近寄つて来た。教師の服装をした男は、何度も首を捻りながら、昂の左脚と右脚の寸法を計算してみたり、終には身長や胸囲まで計つてみるのであつたが、どうも合点が行かないらしく、鉛筆でポンポンと手帳の表紙を叩いてゐたが、やがて手帳を開けて何か書き込んだ。恰度その時、白い上着を着て眼鏡を掛けた医者らしい男が側に近寄つて来て、黙つて手帳を覗き込んでゐたが、何か教師にむかつて合図をした。そこで二人の男は昂をその儘にして、少し離れた場所で、ひそひそ話を始めた。「どうもあの生徒は根性が捩れてるのですが」と教師の興奮した声や、「いや、なあに、私におまかせ下さい」と医者の宥めるらしい声が洩れた。
医者は昂の方に向直ると軽く手招いた。昂が躊躇してゐるのを見物人が後から小衝くので、到頭彼は医者の方へ歩き出す。すると医者は彼が従いて来るのを疑はないもののやうに、ずんずん先に立つて歩き出した。昂は逃げ出したいのだが、逃げると後でどんな乱暴なことをされるかわからないので、厭々ながら引かれて行く。階段を昇り、廊下を廻ると、音楽室があつて、小学校の女教師がオルガンを弾いてゐたが、窓の外を通る二人をけげんさうな顔で見送つた。その音楽室の窓からは川が見え、鯉幟を立てた家も見えた。やがて医者はつきあたりの部屋に入ると、内から鍵を掛けて、大きな机の前の廻転椅子に腰を下した。その部屋は半分板の間になつて、半分畳が敷いてあつたが、秤や、小さな寝台や、抽厘の沢山ある戸棚などが並べてあつた。隅の方に立てられてゐる骸骨の標本が一つ、ガクガクと張子の虎のやうに首を揺らがしてゐた。壁には日本海海戦の油絵が懸けられてゐて、沈没しかかつた軍艦が頻りに真黒な油煙を噴き出し、その油煙がその部屋の天井のあたりの壁を染めてゐた。医者は暫く机の抽厘をあけて何か探してゐたが、不意と昂の方へ向きかはると、側にある小さな椅子を指差して、、「掛けたまへ」と云つた。昂が神妙に椅子に掛けると、医者は今度は聴診器を取出して、それを玩具のやうに弄んでばかりゐた。何時まで経つても落着き払つて、さも娯しさうに医者はそれを弄んでゐたが、時々何か素敵な考へでも浮ぶのか、得意さうに独りで微笑してゐた。ところが突然、医者はハツと昂のゐることに気がついたらしく、ぢつと昂の顔に眼を据ゑてしまつた。それから、ひよいと手を伸して、昂の顎の下を撫で出した。医者の掌は柔かく、撫で方も軽かつたのに、段々昂は呼吸が塞るやうに苦しくなつて来た。血が頭にむかつて逆流してゆく音がドクドクと聞えた。それでも医者は相変わらず静かに今度は昂の咽喉の辺を撫で出した。昂は苦しさに涙がぽろぽろと落ちて、声が出なかつた。やがて医者は手を離すと、今度はさも親しさうに昂を眺めるのであつた。「大分つらさうですな」昂は半分泣きながら頷いた。「ではあそこで横になつたらいいでせう」と医者は畳の方を指差した。それから態々枕を出して呉れた。昂は横になつた。医者は戸棚の小さな抽厘から何か独楽のやうなものを取出した。微かにビユンと鳴る音がするので昂がその方へ眼をやると、医者はその持つてゐたものを軽く空間へ放つた。はじめ虫か何かと思つてゐると、気がつくと、それは一匹の虎であつた。豌豆位の大きさの虎だが、たしかに美しい縞があり、眼球がキンと光つてゐる。その虎は空間を宙に泳ぎながら、次第に昂の方へ近寄つて来る。昂はどう云ふ訳だか、その虎が怖くて耐らなくなつた。虎が進むにつれて、糸に綴られた露の玉のやうなものが三つ四つ前後に続いてゐる。虎は昂の一尺位眼の前に来ると、急に故障が出来たやうに動かなくなつた。が、暫くすると今度は逆の方向にゆつくり進んで行つた。それからまた暫くすると動かなくなり、方向を変へては進み出す。昂は胸が痞(つか)へて、手足が痺れ、額からも耳からもたらたらと膏汗が滲み、どうにもかうにも苦しくてならない。もう昂のまはりの空気はみんな虎に吸ひ採られたのか、無くなつてゐる。昂の眼はぼんやりして、自分の睫と、その辺の畳の筋しか見えない。みんな暗く、みんな苦しさうな影だ。それなのに虎はまだやつて来る。突然、外の方で稲妻がして、バラバラ雨が落ち出したやうだつた。すると、誰か昂の耳許で彼の名を呼ぶ声がした。声は何度もするのに昂には誰だかよくわからない。すぐ眼の前にその男の黒いずぼんがぼんやり見えて来た。「寝てるのかい」とその声は云つてゐるやうで、昂の側に立つたまま頻りにもじもじしてゐる容子であつた。その二本のずぼんの隙間から机が見え、机の上には灰皿と昂の学生帽が置かれてゐる。机の前が窓障子で、その窓は、狭い露次に面した二階の窓だつた。昂はその辺をぼんやり見てゐるうちに、何時の間にか彼の身体は机に吸ひ寄せられて、机に凭掛つてゐた。
突立つてゐた男はそのうちに昂の正面へ来て畳の上に膝を組んで坐つたが、その友達はだれであつたのか、昂にはまだ呑み込めなかつた。てらてら光つた大きな鼻をした、顎の広い、どつしりした男であつたが、大変腹を空かしてゐる容子で、顳_(こめかみ)には玉の汗が浮上つてゐた。その顔を見てゐるうちに昂も顳_に汗が出て、自分も同様に饑じくなつて少し目が昏んで来た。ふと眼の前に口を開けた蝦蟇口が見え、その暗い底の方に五十銭銀貨が一枚ぼんやり見え隠れしてゐた。ところが、昂の前にゐる男は饑さに耐へかねて、あくびとも溜息ともつかぬ息を吐いた。すると、その男の大きな顔は段々痩せ細つて来て、前とは見違へるやうな、まるで消え入りさうな顔になつてゐた。その男は余程睡眠不足とみえて、眼を開けてゐるのもつらさうに、一秒、一秒の時間の重みにも、神経が削り奪られて行くらしく、豆粒程の瞳から気違のやうな切なさうな光線を閃かしてゐた。ぼんやりと眺めてゐる昂の方でも、もう二三秒もしたら宇宙が爆発するのではないかと、そんな危険な不可知な装置が今眼の前の空間にしつらへられてあるのを感じさされた。それで、昂の眼球も乾ききつて、眼の底の方に熱い濁つた涙が貯へられて行つた。到頭その友達は、わあ、と口をあけると、全身全霊の疲労を吐き出すやうに、苦しさうなあくびをした。それから頭をがくりと、前の方へ一度突落して再び上に挙げると、もうその友達の顔はすつかり刃のこけた剃刀のやうなものに変はつてゐた。その男は時々誰かに背骨をどやされてゐるやうに、がくりがくりとしながら、それでも一生懸命、昂の机の上を眺めてゐた。昂はその男が何故一生懸命、机を眺めてゐるのか、段々心配になつた。と、間もなく友達は畳の上に打伏せになると、咽喉を痙攣させてばたばたし出した。友達は唸りながら、白い液体を吐き出した。それから大きな溜息をついて、横になつたが、段々気持が落着いて来るらしく、眼を天井へやつてゐた。
ふと、友達は昂の方を見ながら、「おい、外へ出ようぢやないか」と云つて立上がつた。たつた今あんなに苦しげにしてゐたのが、もう打つて変つて元気になつてゐるのだつた。昂もそれに釣込まれて、立上らうとしたが、どう云ふものか、腰に力がなく、脚がふらふらし出した。友達は昂のまごまごしてゐる様子を珍しさうに見返して、「お前歩けないのかい」と訊ねた。それで昂は無理矢理に立上がつて、よろよろと歩き出した。すると友達はもう昂が歩けるのを疑はないもののやうに、ずんずん先に立つて歩き出した。何時の間にか二人は細い裏町を抜けて、大通りへ出てゐた。昂は段々心細くなり、外に出たことを後悔した。一足毎に息切れがして、今にも身体が倒れさうになつた。眼の前に電車や自動車が疾走してゐるのが、情なかつた。もうこれきり帰れないのではないかと思はれた。足許を見れば、木製煉瓦の敷詰められた鋪道に、自分の下駄が吸ひ込まれて行きさうだつた。もし今膝のところから力が抜けると、そこへ倒れてしまふのだが、……さう思ふと却つて早く倒れてしまひ度くもなるのだつた。友達の方は靴の音もはつきりと自信ありげに歩いてゐた。そのうちに、たうたうと水の響がして来た。気がつくと、さつきまで一緒だつた友達は、もう彼を見限つて勝手な方向へ行つてしまつたらしい。路は何時の間にか、大きな石塊のごろごろしてゐる下り坂になつてゐる。昂の下駄は石に躓いて、時々よろめいた。かうして歩けるのが不思議な位だ。空気は冷々として、霧が這つて来る。忽ち霧は両側の杉を包み、ばらばらと滴がしたたる。水の音は段々近づいて来るので、昂はもう一呼吸だと云ふ気持がした。ふと見ると、崖の方には萩の花が咲いて、だらりと垂つてゐた。そこにも銀色の霧が降つてゐた。足許の方には紫陽花も咲いてゐる。その側に矢印で方向を示した小さな札が立つてゐる。昂は到頭そこへしゃがんで、息切れを直さうとした。急に咽喉が締めつけられるほど切なくなつて、涙がぽろぽろと両頬に流れた。冷やかな空気の迫力が一層彼の心臓をずきんとさせた。だが、暫くすると昂はまた立上がつて歩きだした。もう苦しさは以前よりも大分減つて来た。それに谷川の音が今はすぐ足許に聴かれるのだつた。昂は橋を渡つて広い道へ出た。
そこに藤棚のある茶店が一軒あつて、バスの停留場があつた。昂がそこへ立止まると、大きな、黄色いバスがやつて来た。昂は今、救はれたやうにそのバスに乗った。乗客は他に誰もなかつた。昂は緑色のクッションに腰を下し、低い天井を眺めた。運転台の方にはセルロイドのがらんがらんが吊つてあつた。濃霧と小雨とで、ウインドウ・クリーナアが揺れてゐた。大きな硝子窓に、周囲の景色が移動した。バスは渓流に沿つて山路を廻り、村落を過ぎて進んだ。やがて、雨もはれ、眺めも広々として、日が輝き出した。雨のはれた山脈がむかうに見えた。むかうには竹薮も見えた。美しい緑の並木路もあつた。その時、運転台の方にゐた女車掌が静かに昂の側までやつて来た。その女車掌は立つたまま、窓の外を指差しながら歌ふやうに喋り出すのであつた。
――御覧なさい、あのむかうに見へます山々はまるでこの世のものとも思はれぬほど美しいではありませんか。静かに静かに時間の流れのなかに聳えて、何時までも何時までも、あなたを慰めてくれるのであります。雨が降れば濡れ、日が照れば輝き、朝は朝の姿で、夜は夜の姿で、昔からずつとあそこにあるので御座います。
それにあのなだらかな緑の傾斜はまた何と云ふ優しい眺めなのでせう。ああ云ふものを御覧になると、人間のかたくなな心は何時の間にかすつかり消えて行つて、あなたはむかし、むかしにかへつてゆくのです。
あなたはお母さんの懐にいだかれてゐた子供の頃を憶ひ出しませんか、あのお母さんの白い胸を見上げながら、夢みてゐた夢があの山なのです。そら、あの山腹の方には白いふはふはの雲が浮んでゐて、あそこで静かに睡つてゐるのです。
広島花幻忌の会『雲雀』第4号、2004年、47~58ページより
(初出は「三田文学」昭和12年5月号)